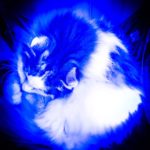Label – Creation / Domino
Release – 1991/11/04
2021年11月4日、My Bloody Valentineが1991年にリリースした2ndアルバム『Loveless』が30周年を迎えた。これを記念し、弊メディアではライター陣三名によるクロスレビューを実施。後追い世代である我々だからこその視点を通し、それぞれの聴取体験や捉え方の相違などから、まだまだ語り尽くされていない『Loveless』における再確認/再発見を少しでも多く提供できれば幸いである。
* * *
■ 鈴木レイヤ
出会いは高校一年生の頃だった。バカげた休日の午後ですべきこともせず、中学から割にストイックに続けていた部活を突然に退部してだらだら生活していた時期だったので妙に間延びした時間ばかり流れていた。その日、家には誰もおらず自分はひとりでこたつに入り文字通り何もせず猫をずーっと眺めていた。動くのはその猫とTwitterのタイムラインだけだった、怠惰という単語におこがましいようなラベルの貼りようがない、特筆すべきことの全くない午後だった。カーテンを開け放ったままのリビングの窓、外で早い蝶が舞っていた。レース越しの絶妙な明るさの下で、出かけた家族の帰りを気にしながら何度か自慰をした。これが状況だった、その日は『m b v』の解禁日か何かだったのだろう、毎秒見ていたインターネットがざわついたので興味本位でYouTubeを開き、そのバンドの名盤、金字塔とされている作品を聴いたのだ。
音は文字通り枯れていた。iPhone 4sという当時にしては新型のスマートフォンとYouTubeが音楽に触れるツールだった。音量は最大にまで上げられていた、しかし響いた音は貧弱だった。イントロのスネアは四度叩かれた、今でこそ凶暴という言葉で理解しているあれはその日「パンパンパンパン」とかなり乾いていた。ヴォーカルをサンドペーパーが包んだような音楽が始まると乾きを無視し溶け渦巻いていた。窓の外では前述の通り蝶が飛んでいた、こたつの上には丸めたティッシュペーパーがいくつか乗っていた。自分は生の腹の上に薄っぺらなスピーカーをつけたiPhoneを乗せて、天井でゆっくり回るファンを眺めていた。ジャージを履いた下半身はこたつの中で火照っていた。つまりその経験はサイケデリックだった、環境のせいで本来突きあがるべき感動が存在せずどろどろした時間をその音楽はかき混ぜ続けていたのだ。
ダメなスピーカーで『Loveless』を聴いたことがある人には分かるかもしれない、あの音楽はサンドペーパーをまとっているにも関わらず、摩擦をゼロにする。そして、慣性を永遠にした。夢とは逆のことが起こっていた、音楽は僕を包むことはなくただ腹の上で小さくうごめいていた。僕にしちゃ何年振りでもなかったし、伝説のバンドでもなかった。おそらくイヤホンを付けたところでヴィレッジ・ヴァンガードで購入した2,000円のピンクの安物だったのでたいして変ることはなかっただろう。初めて聴いた時『Loveless』を外から眺めたのはむしろ良い経験だったのかもしれない。シューゲイズという言葉は知らず、My Bloody Valentineに対する畏怖も持っていなかったそんな人がぼろくそのスピーカーで聴けば音同士が潰しあって、ジャージャーシャーウゥーンと聴こえるのみに過ぎない。自ずと浮かび上がる大まかな音の形に安心を感じた、輪郭に線を引くことの出来ないあの形に覚えた感覚は今でも説明の出来るものではない。
トレモロのせいか午睡の間近で戸惑う自分の瞼の裏は動いていた。あの日僕はそのまま昼寝になったのだろうか? 夢とは逆だ、終わりを覚えていることは出来ない。覚えられることのない時間にも『Loveless』は含まれていただろうか?
今でも、それぞれのギターが身を捩っているようなバランスで寄ったり離れたりしていくのを聴くと奇妙な感覚に陥る。後半へ差し掛かるに連れて粒立ちと繰り返しの予測がきくようになるのは覚醒しそうでしないものだ。酒、麻薬と同じで自分が正当な判断を下していると自信過剰になっているだけ。『Loveless』をぐるぐると回っていると、とろくさい者同士の人間関係のように苛立ちやもどかしさをまず覚える、しかしやがて安楽も知っていく。このアルバムは正しいものに見える、また帰るべきだった場所に来たような気持ちになるのだから──しかし同時に居心地悪くもある、断りなしにおかしなところを撫でてくるからだ、快感であるか否かは問題ではない。これは正義やらそういう判別しやすいものでは決してなく、何者にも影響しない存在だ。肯定でも否定でもなくただisnessだけを提示するような、受け入れもせず突き放しもせず、また受け入れ突き放しながら、存在を承認してくれるものだ。我々が生きていた中で無意識に存在を取り消した感性を『Loveless』は含んでおり、人は必ずそれに向き合い開き直り、愛し直さざるを得ない。
* * *
■ 鴉鷺
1991年、幻想郷への開かれた扉としての音楽であり、ギター・ノイズへの革新的なアプローチであり、定型化したロックを変貌させる劇薬であり、不幸にもロックに内在しつつあったマチズモの解体であり、後の多様な傍流の先駆けである作品がリリースされた。
印象的なスネアの連打の後、まず耳に飛び込んでくるのは美しい、今までのどんな作品にも似ていない強烈なギター・ノイズである。「Only Shallow」を最初に聴いたリスナーが覚える未聴感はシューゲイザーのある種の共通した体験として挙げられるだろう。幾重にも多重録音された強靭なギターと天上のヴォーカルはCocteau Twinsの諸作を想起させつつ全く新しい音響で、その二つのパートが表出させた固有の幻想性はシューゲイザーという音楽、強く言えばカルチャーの核を成す重要な要素として捉えられる。ヴォーカルの対位法的な旋律も重要で、(そもそもロックに限らず重要な技法ではあるが)My Bloody Valentine的なヴォーカルの和声の用い方は重要な手法として普及している。
「Loomer」で聴き取れるのは、ストーンしたパンク・ロックのような前のめりに突き進む展開と、全曲に通底するエンジェリックなヴォーカルだ。全曲を通して最もヘヴィーなギターが響き渡る中で展開されるエセリアルなヴォーカル、という展開は後のヘヴィー・シューゲイザーの先駆けと言え、同時にMy Bloody ValentineがRamonesやBuzzcocksを筆頭とするパンクロックから多大な影響を受けたことの証明だろう。
間奏曲を挟み、アルバムの一つのピークである「To Here Know When」が始まる。徹底してヘヴィーで、ディレイとリヴァーブでアンビエント・ドローン化した特徴的なギターがこの曲の前衛性を定義している。その轟音が響く中でアルバムでも屈指の美しさのヴォーカルの旋律が展開されるこの曲は、後のLovesliescrushingやBuddhas On The Moonといったアンビエント・ドローン化したシューゲイザーの重要な参照元であり、『Loveless』という作品の中でも最も多幸感に満ちている。
「To Here Know When」を聴取する瞑想的な体験を打ち破るように、「When You Sleep」という至上の楽曲が始まる。前曲のドローン的な引き伸ばされた時間感覚が、この一曲でポップソングの瞬間の美学に塗り潰される。The Velvet Undergroundのような実験的ロック・バンド、もしくはLa Monte Youngのようなドローン・ミュージックからRamones直系のポップセンスを持ったパンク・ロックという彼らの系譜を思い起こさせる瞬間だ。明快で暗さを感じない、パンク・ロック直系のシンプルでアッパーなコードとピッチシフトされた象徴的なケヴィン・シールズのヴォーカルが印象に残らないリスナーは存在しないと思われる。それと同時に、My Bloody Valentineのパブリック・イメージに近い楽曲でもあるのではないだろうか。
ここから先のポップソングの美しい流れはシューゲイザー史のみならず、ロック・ミュージック、もしくはポピュラー・ミュージックの歴史に記述され続ける瞬間の連続だろう。「I Only Said」の気怠く優美な瞬間がエモーションの極点を連続的に記録する体験は間違いなく彼ら固有の作風だ。そしてスローな「Come In Alone」にも共通して表現される気怠さは、間違いなく前述したThe Velvet Undergroundの系譜、恐らくNicoに寄る所が大きい作風だろう。彼らのデビュー作である『This is Your Bloody Valentine』を聴くと、最初期はゴシックな要素があるガレージ・ロックが演奏されている。そこに明らかな当時のゴシック・ミュージック、恐らくポスト・パンク勢の影響を聴き取ることができ、その系譜、つまりヴェルヴェッツだけではなくそれ以降のNicoの作品群の影響を聴き取れる、と考えたくなるのは筆者のファン心理に寄るものだろうか。
鋭く歪み、潰れたノイズ・ギターの持続音と囁くようなケヴィン・シールズのヴォーカルが聴者に強い印象を残す「Sometimes」もヴェルヴェッツ以降の美しい達成と言えるだろう。ギターが軸となる持続するノイズはジョン・ケールのチェロのドローン感覚を思い起こさせるし、その上で旋律を展開するシンセサイザーは「Sunday Morning」の鉄琴のようだ。そしてケヴィン・シールズの、退廃的だが闇に沈み込まない倦怠したヴォーカルは、明らかにルー・リード以降であると筆者には聴こえる。
「To Here Know When」と並んで幻想的な「Blown A Wish」は、前者をポップ・ソングの文脈で再解釈、もしくは解体と再構築を行ったような優れて耽美な楽曲だ。弦の響きを僅かに残しながら持続し、美しいドローンを表現するギターとビリンダ・ブッチャーの作中でも秀でて鮮やかなヴォーカルの対位に魅了されたのは筆者だけではないだろう。音楽、ひいては芸術に美への信仰とそれ以降の美しさそれ自体への奉仕という要素があるなら、音楽史上でも際立って高い水準で達成したのがこの楽曲というのが(言い過ぎかもしれないが)筆者の見解と記しておく。
音楽は速度を上げ、「What You Want」というMy Bloody Valentineのパブリック・イメージをある意味で体現する、明快でキャッチーな楽曲に辿り着く。この楽曲の強靭なギターのサウンドは後の轟音シューゲイザーのバンド群にも継承され、もしくは参照されているだろう。ビリンダ・ブッチャーのコーラスとケヴィン・シールズの歌う主旋律の交錯が美しい。
そして最終曲の、作中で最も長尺であり同時にビートやリフレインの実験でもある「Soon」で、このアルバムは幕を閉じる。抑制が効いたイントロのギター・ノイズと打ち込まれたビートが、チェンソーのように空間を切り裂くギターに破られる瞬間を起点として、ヴォーカルの旋律に伴って感情が極点に導かれる体験は稀有なものだろう。その展開が徹底的にリフレインする、ある種のトリップの様であり瞑想の旅のようでもある体験が、それ以前のロック・ミュージックに存在したとは思えない。あるとしたらポップ・ソングの瞬間の美学やドローン・ミュージックの持続する瞑想的トリップに要素として存在したものと思われ、単純なパスティーシュの否定を経て、音楽の要素を断片の提示ではなく再解釈と構築を経た上での表現として成立させた彼らの手腕が伺える。
瞑想的ドローンや実験的ロック・ミュージック、オルタナティヴ・ロックやパンク・ロックの瞬間の美学、ビート・ミュージックのリズムやリフレインの実験を継承と再解釈、もしくは解体と再構築を行った上での音楽であり、定点に決して留まる事のない芸術的遊牧の音楽である『Loveless』が示した音楽上の達成はそれ以降のシューゲイザーの流れを生み、ある意味で決定付けた芸術至上の一つの到達点と言える。この不朽の名盤を今後も聴いていくのは実り多く充実した体験で、個人的な必然でもあるだろう。
* * *
■ 對馬拓
あえて言ってしまいたい、淡いワインレッドのジャケットを手に取ったのが運の尽きだった。盤を再生した途端、耳に打ち付けられるスネア。それは自分自身の中にあった旧来の価値観が瓦解へと向かうカウントであり、未知の享楽への扉をノックする音に他ならなかった。
いや、初めからポジティヴな感覚を見出せていた訳ではない。今だからこそ言えるが、最初の摂取は身体が生理的に拒んでしまった、というのが正しいかもしれない。理解の範疇を超えた音楽だった。「Only Shallow」のイントロの、津波のようにうねりながら押し寄せるあのサウンドが何の楽器から発せられているのか、当初はまるで見当がつかなかった。その後YouTubeに上がっていたMVを観ると、ギター、ドラム、ベースといった極めてオーソドックスなバンド編成で演奏しており、一層困惑させられた。何をどうしたら、こんな音が出るのだろうか……?
無理もない、MVでは体裁的に四人が演奏しており──まあ実際ライブでは四人が飛行機のエンジン並の轟音を黙々と放ち続ける訳だが──何の知識もなければ音源上も全員で奏でているように思えてしまう。しかし、「Only Shallow」だけではなく『Loveless』というアルバム自体が、実はケヴィン・シールズという天才による事実上のソロ・プロジェクトで、作品全体を覆うあの不可思議なサウンドはリヴァース・リヴァーブやサンプリングといった実験の集積であり、ギターが秘めるポテンシャルを限界まで押し広げた極北的なアルバムとして君臨している……などという事実は後に知ることで、当時の自分はただやり場のない、不快でもないが決して快楽でもない、曖昧な居心地の悪さが心臓の底の方に溜まっていく、そんな奇妙な感覚に支配されていた。
ところが、彼らが放つ強烈な磁場に抗うことなど不可能だった。貪るように何度も摂取するうち、『Loveless』を理解したタイミング、言うなれば享楽的な感覚を抱くようになった瞬間というものが確かに存在したはずなのだが、その境界すらも曖昧だったように思う。いつしか耳にこびりついたあの轟音をとにかく追体験したいという欲求を、とっくに抑えられなくなっていた。『Loveless』はそうやって聴覚から五感全体を侵食し、体内から揺さぶりをかけてくるアルバムであり、数多の人々の人生を狂わせた作品であることは周知の通りであろう。
当然、万人受けする類の音楽ではない。ある者はどこまでも耽溺し、一方で、ある者は完全に拒絶する。『Loveless』はその特異なサウンドで聴く者の評価を二分する作品でもある。一部ではミーム化し、海外のリスナーが「vacuum(=掃除機)」などと揶揄するのを見かけたこともあった。正直、無理もないだろう。ただ、ケヴィン・シールズは「最初に自作したレコーディング音源、あれにメインで使った楽器は掃除機だったんだ」と最近のインタビューで語っている(別冊ele-king『マイ・ブラッディ・ヴァレンタインの世界』p.36より)。当時ケヴィンは11歳頃で、家にあった録音機での遊びだったという。それを知ってか知らずか、「vacuum」という表現は根源的な部分をある意味言い当てているのが何とも面白い。もちろん『Loveless』の轟音が掃除機そのものだ、などと言うつもりは微塵もないが、ケヴィンが幼少期からノイズ・ミュージック(的なもの)に対して、ある意味で美意識に近いものを見出していたことが垣間見える貴重な発言であることは間違いない。
ノイズは美しい。ケヴィン・シールズは、当時ほとんど崩壊しかけていたバンドをどうにか繋ぎ止めるかのように孤独な作業を続け、ついには『Loveless』を完成させ、そのことを圧倒的に証明してみせた。デビー・グッギは一切ベースを弾いておらず、コルム・オコーサクも体調が悪化しドラムを叩ける状態ではなく、「Touched」以外のドラムはケヴィンによる打ち込みがほとんどであり、ビリンダ・ブッチャーとケヴィンは私生活におけるパートナーとしては破局。さらにはスタジオのたらい回しや機材トラブル、エンジニアの不理解、レーベルとの確執──と文字通りラヴレスな状況。ケヴィンはそれでも何もかもを投げ出すことなく、持ち前の完璧主義的な気質を存分に発揮し、ロック・ミュージックにおける価値観をひっくり返した。ノイズは得体の知れない雑音、不快で排除されるべきものなどではなく、むしろ徹底的にコントロールすれば胎内に回帰するかのごとく夢幻の安寧をもたらし、陶酔的な芸術たらしめることが可能だという事実を、たった一枚のアルバムで、しかもほとんど一人で宣言してみせたのだ。余談だが、KrausやParannoulなど、今年新作をリリースしたソロ・シューゲイザー勢は、遡ればケヴィン・シールズの姿に重なる部分があるのではないか、と考えたりもする。
とにかく、そうしたある種のケヴィンの執念は、極東の島国に住む一介の大学生にも突き刺さった。一度身体が覚えてしまった「合法的な享楽」を手放す人間など、よほど禁欲的でない限り不可能に近いだろう。『Loveless』は未体験の感覚に満ち溢れていた。音楽に対して所謂「白昼夢」的なニュアンスを感じたのは「To Here Knows When」が初めてだった。前衛的でノイジーなサウンドの中にもポップ・センスを同居させられることに気づけたのは、「When You Sleep」や「I Only Said」の存在があったからだ。あんなに拒絶していたのに、今となっては「Come in Alone」のメロディーは涙が出るほど美しいと思う。『サ道』において、主人公の一人である蒸し男は「サウナは思考から感覚の世界に切り替わる」と持論を展開していたが、その文脈で言えば『Loveless』を通して得られる体験はまさにサウナ的であり、邪念としての思考を排除し、本能的な感覚を呼び起こす。そして、その度合いはダンサブルな「Soon」で頂点を迎えるのだ。自身における感覚のコペルニクス的転回、言うなれば音楽の受容態度におけるパラダイム・シフトは、間違いなく『Loveless』がもたらしてくれたものだった。
リリースから30年。1992年生まれの自分にとっては、当時のシーンや空気感、リスナーたちの反応などをリアルタイムで知ることは不可能だ。しかし、こうして自分の中で一向に鳴り止まない音楽として存在するに至り、また『Loveless』に影響を受けた音楽が生まれるのを今も次々と目撃している。それならば、この現象を可能な限り見届けたい、浮遊する感覚の海に身を任せ、永遠を漂っていたい、そう願う。
Author